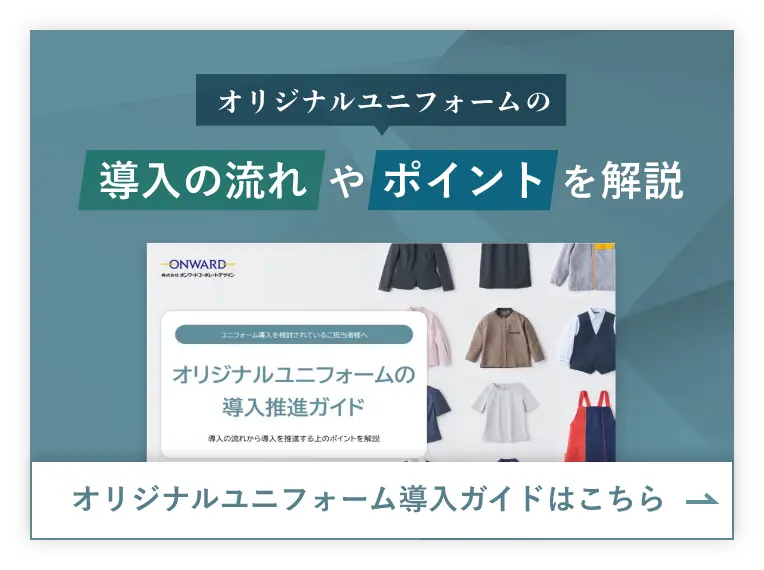なぜ今、企業イメージが問われるのか

現代はSNSやレビューサイトを通じてユーザーが企業の評価を発信し、それが瞬時に広まる時代です。一度のトラブルや不適切な対応が炎上を招き、企業イメージを大きく損なうリスクがかつてないほど高まっています。企業イメージが悪化すると、さまざまな面でリスクが生じます。企業イメージを損なうことによるリスクは主に以下の3つがあります。
トラブル発生時の信頼回復が困難になる
信頼されている企業は、問題が発生しても適切な対応を取ることで、顧客や取引先から理解を得やすくなります。一方、イメージが悪化している企業は、不祥事が起きた際により厳しい目で見られ、批判や炎上のリスクが高まります。その結果、ブランド価値の回復が難しくなり、企業にとってさらなるダメージとなります。
採用や人材確保に悪影響を及ぼす
求職者は企業の評判や働きやすさを重視する傾向が強まっており、企業イメージが悪化していると応募が集まりにくくなります。また、既存社員の離職が進むことで人材の流出が加速し、結果として人材不足や成長の停滞といった問題につながります。
売上に影響する
現代の消費者は、製品やサービスの価格・機能に加え、企業の理念や社会的責任にも関心を持っています。企業イメージが悪化すれば購買意欲が低下し、競合他社への流出が進みます。さらに、悪評がSNSや口コミで拡散されることで、ブランド価値が一層損なわれ、長期的な売上減少につながる可能性もあります。
このように、企業イメージは信頼の維持・人材の確保・売上の維持といった重要な経営要素に直結しています。では、企業イメージは何によって形成され、左右されるのでしょうか。次章では、企業イメージに影響を与える主な要因について詳しく見ていきます。
企業イメージを左右する要因とは
企業イメージを形づくる要因には、すべての業界・企業に共通するものと、各業界に特有のものの2種類があります。ここではまず、業種を問わず企業イメージに影響を与える共通要因を整理したうえで、製造業・サービス業・IT・金融など、業界ごとの特徴的な要因についても見ていきます。
企業イメージを左右する共通要因
ブランドの一貫性
企業が持つブランドは、企業イメージを形づくるうえで中核的な役割を果たします。そのため企業が伝えるメッセージと実際の顧客体験にズレがあると、顧客は違和感を覚え、企業への信頼が損なわれることがあります。
たとえば、製品発表イベントや広告で「革新性」や「未来志向」を強く打ち出しているテクノロジー企業が、自社のWebサイトでは古いデザインのままで更新されておらず、言葉づかいも時代遅れな印象を与えていた場合、顧客はそのギャップに違和感を抱きます。重要なことは、企業のブランドを広告やプロモーションだけでなく、あらゆるタッチポイントで同一のブランドとして認識できることです。 それにより、ブランドイメージが着実に定着しやすくなり、企業に対する信頼感につながります。
顧客体験(UX)
顧客体験(UX)とは、製品やサービスの使いやすさや品質に加えて、購入前後のサポート対応や問い合わせ時の印象など、企業と顧客が接するあらゆる場面での体験全体を指します。こうした一連の体験を通じて、顧客が感じたことや受け取った印象が企業イメージを形づくる要因となります。 企業がどれだけ意図的に姿勢や取り組みを示していても、最終的には顧客一人ひとりの体験を通じて、その企業らしさが捉え直され、イメージとして定着していくことになります。
企業の社会的責任(CSR)
現代の企業は、単に利益を追求するだけでなく、社会的な責任を果たすことが求められています。環境への配慮や地域貢献活動は、企業の信頼度を向上させ、顧客からの支持を得る上で重要な取り組みです。例えば、エコフレンドリーな製品の開発やサステナブルな経営方針など、社会的な姿勢が明確に打ち出されていると、それ自体もブランドに影響を与える要素の一つとなり、企業イメージの形成に影響します。
危機管理と評判(不祥事対応、リスクマネジメント)
企業が不祥事や危機的な状況に直面したとき、その対応の仕方がブランドの評判に大きな影響を与えます。適切なリスクマネジメントや迅速かつ透明な情報提供を行うことで、企業の信頼性は保たれます。一方で、不適切な危機対応がメディアやSNSを通じて可視化されると、それも企業に対する信頼低下の要因になり、企業イメージを傷つけることにもつながります。
従業員の姿勢(社内文化、エンゲージメント)
従業員のモチベーションや企業文化は、外部から見た企業イメージにも直結する要素です。従業員が企業のビジョンや目標に共感し、高いエンゲージメントを有していると、その姿勢が顧客との接点にも表れます 。この表面化した姿勢が、顧客にとっての企業イメージを形づくる重要な要因の一つになるのです。
主な業界ごとの要因と特徴
製造業:品質と技術力の可視化が信頼の鍵
製造業においては、製品の品質の一貫性や技術力の高さが、企業イメージを支える最も重要な要因です。厳格な品質管理体制や高い安全基準の順守、そして新技術の導入姿勢などが、「信頼できる製造企業」としての評価につながります。
顧客は、製品の性能や不具合時の対応といった体験を通じて、企業の信頼性を実感していきます。また、展示会での技術紹介や公式サイトの製品説明など、視覚的・言語的な情報によって企業の価値を具体的に認識し、「この企業は高品質で信頼できる」というようなイメージを自ら形成していきます。
サービス業:接客の一瞬がブランド全体を左右する
サービス業では、接客対応の質や店舗の雰囲気が企業イメージを形づくる中心的な要因です。特に、スタッフの態度や言葉遣い、サービスの迅速さ、空間の清潔感などが顧客の印象に強く影響します。従業員のユニフォームのデザインや清潔さも、視覚的にブランドイメージを伝える重要な要素となります。
顧客は、店舗やサービスを利用する中で、スタッフとのやり取りや店舗環境などを通じて企業の姿勢を感じ取ります。さらに、SNSでの反応やWebサイトの世界観など、あらゆる顧客接点を通じて総合的な判断がなされ、結果として「丁寧な企業」「信頼できるブランド」といったイメージが形づくられます。
IT・テクノロジー業界:使いやすさと安心感の両立が不可欠
IT・テクノロジー業界では、ユーザー体験(UX)とセキュリティ対策が、企業イメージの基盤となります。直感的な操作性や、期待を上回る機能性は、革新的で信頼できる企業という印象を与えます。一方で、情報漏えいやセキュリティ不備への懸念は、企業への評価を大きく損ねるリスクを伴います。
顧客は、日々のサービス利用の中で、利便性や安全性を通じて企業の技術力や信頼性を感じ取ります。特に、ログインやデータ処理、サポート対応など、日常的な使用体験が蓄積されることで、企業イメージは段階的に形づくられていきます。
金融・保険業界:透明性が信頼を築く土台に
金融業や保険業では、信頼性と透明性、およびセキュリティへの取り組みが、企業イメージの中心的な要素です。顧客の財産や個人情報を預かる責任の重い業界であるため、説明責任や情報の明快さ、リスク管理体制の整備などが不可欠となります。
顧客は、契約プロセスでのやり取りやWebサイトでの情報発信、問い合わせへの対応を通じて、企業の誠実さや信頼性を評価します。そうした積み重ねが「安心して任せられる企業」という長期的なイメージへとつながっていきます。
以上のように、企業イメージを形成する要因には、UXやリスクマネジメント、社員のエンゲージメントなど、すべての業界・企業に共通するものから、各業界に固有のものまで、さまざまな要素が複雑に絡み合っています。いずれにしても、企業が意図したブランドイメージを顧客の中に着実に築いていくためには 、企業としての一貫した価値観や姿勢を発信し続けることが重要です。
では、具体的に企業はどのような取り組みを通じて、自社のイメージをより良いものへと導いているのでしょうか。次章では、企業イメージの向上に寄与する代表的な施策について、さまざまな角度から考察していきます。
企業イメージ向上の取り組みには何があるか

製品・サービスの品質向上
製品やサービスの品質は、顧客にとって最もわかりやすく、企業への評価に直結する要素です。企業イメージを高めるには、まずこの「当たり前」と思われがちな品質向上の取り組みを、いかに実直かつ継続的に実行しているかを示すことが鍵となります。特に、顧客から寄せられるフィードバックを、単なるアンケート結果にとどめず、商品改善やサービス設計にどう反映させているかが重要です。
たとえば、購入後に寄せられた意見をもとに商品仕様を変更したり、問い合わせの傾向からマニュアルを見直したりするなど、具体的な改善につなげることで、企業姿勢への信頼が積み重なります。さらに、アフターサービスの充実は、リピーターの獲得や口コミの広がりにもつながり、結果として企業イメージの向上に直結します。
社会的責任(CSR)・サステナビリティへの取り組み
環境や社会に対する責任を果たそうとする姿勢は、企業の信頼性を裏打ちする要素としてますます注目されています。CSRやサステナビリティに取り組む際には、SDGs(持続可能な開発目標)の中から自社の事業と関連性の高い目標を選定し、どのような形で貢献できるかを検討することが求められます。
たとえば、製造業であれば「つくる責任 つかう責任(目標12)」に基づき、廃棄物削減やリサイクル素材の活用といった取り組みが考えられます。また、「地域社会への貢献」といっても抽象的なスローガンではなく、地元の学校や福祉施設との連携、地域清掃活動への参加、災害時の支援といった、地域と継続的な関係を築く実践が求められます。こうした姿勢は、環境配慮や地域共生に真摯に取り組む企業としての印象を醸成し、結果的に企業イメージの向上につながる取り組みの一つとなります。
広報・情報発信の強化
どれだけ良い取り組みをしていても、それを社会に正しく届ける手段がなければ、企業イメージの向上にはつながりません。そこで重要になるのが、情報発信の戦略的な整理です。
プレスリリースは主に報道機関や取引先・関係先企業を対象とし、社会的な信用や事実の公表に適しています。一方、SNSは消費者との日常的な接点として、共感やファンづくりを担います。また、Webサイトはあらゆるステークホルダーに対し企業の理念や活動を体系的かつ継続的に発信できる場であり、これら三者の役割を明確に区別しながら運用することで、情報がより効果的に伝わります。
さらに、発信内容の正確性を保ち、必要な情報を積極的に開示する姿勢である「透明性の維持」も、企業イメージ向上において欠かせない要素です。透明性とは単に情報を公開することではなく、「何を」「なぜ」発信するのかを明確にし、都合の良いことだけでなく課題や改善の方向性も隠さず示すことを含みます。たとえば、環境対策の進捗や従業員の働き方改革の課題など、リスクを伴う情報も含めて適切に伝えることで、企業の誠実さが伝わり、社会からの信頼を得る基盤が築かれます。
こうした発信姿勢の一貫性は、単なる広報活動を超えて、企業そのものの価値観や姿勢を社会に伝える手段となり、結果として企業イメージの向上につながります。
従業員のウェルビーイング向上
近年、企業イメージの評価軸として、社外だけでなく社内への配慮も重視されるようになっています。従業員一人ひとりの健康や満足度を高める「ウェルビーイング」の観点からの取り組みは、企業文化そのものの魅力につながり、採用活動や社外からの評価にも好影響を与えます。
たとえば、健康経営を導入する際には、単なる福利厚生の拡充にとどまらず、健康診断結果の活用や生活習慣改善のための研修などを通じて、継続的な取り組みに発展させていくことが求められます。また、メンタルヘルス支援としては、カウンセリング体制の整備、ストレスチェックの実施、社内の相談窓口の設置などが挙げられ、従業員が安心して働ける環境の土台になります。
これらの取り組みは、外部から見た企業の姿勢や価値観にも直結し、単に「働きやすい職場」として評価されるだけでなく、社員を大切にする企業としてのポジティブなイメージの醸成につながります。結果として、対外的なブランド力の強化や、共感を生む企業像の構築に寄与します。
ブランドを表現しているアイテム・シンボルの見直し
ロゴ、コーポレートカラー、Webサイトのデザイン、社用車のラッピング、社員が着るユニフォームに至るまで、こうしたビジュアル要素は企業の“顔”としての役割を果たします。ただし、これらを定期的に見直すべきかどうかは、単なる流行の変化ではなく、企業イメージとの整合性に基づいて判断する必要があります。
たとえば、企業の方向性が変わったとき、あるいはイメージが誤解されている、古くなって見えている、あるいはターゲット層と合っていないといった課題が生じているときにこそ、アイテムやシンボルを再設計するタイミングといえます。見た目の変更は、内部の変化を外部に伝える重要なサインでもあり、企業イメージの再定義につながる強力な手段となります。
以上のように、企業イメージを高めるには、製品の品質向上、CSRや広報活動の推進、従業員の職場環境の改善など、企業のあらゆる側面にわたる取り組みが重要となります。
「ブランド表現の見直し」は企業イメージ向上になぜ有効であるか

企業のブランド要素が共有・拡散されやすい時代に
前述したブランド表現の見直しは、企業の認知度や信頼性を高め、企業イメージを向上させる上で非常に効果的です。ロゴやコーポレートカラー、広告、Webサイトのデザインなどを刷新することにより、企業はブランドの新しい方向性や価値観を顧客に明確に伝えることができます。
特に近年では、企業はWebやSNSを通じて広範囲にわたって情報を発信しており、ユーザーが企業のサイトや広告、SNS投稿を目にする機会が増えています。また、企業が発信するものだけでなく、顧客が投稿したコンテンツも拡散されやすい状況にあります。そのため、ユニフォームや従業員の姿勢、店舗の内装など、企業と顧客とのコミュニケーションに関連するあらゆる要素がブランドイメージに与える影響は大きくなっています。
このように、ブランド表現を見直すことで企業は顧客に対して新たな印象を与え、長期的には市場での競争力を高めることも可能です。特に、従業員のユニフォームや企業のロゴ、Webサイトのデザインなど、企業の顔となる部分の刷新は、企業の姿勢や価値観を端的に示し、顧客との信頼関係を深める効果的な手段となります。
ユニフォームが企業イメージへもたらす影響
ユニフォームが企業イメージに与える影響が大きい理由として 、ロゴやWebサイトなどのほかのブランド表現と比較して、企業の姿勢や価値観をリアルタイムで伝えることができる点にあります。
WebサイトやSNSは手軽に企業と顧客が接点を持てる場所ですが、これらは一方向的な情報発信に過ぎず、受け手と企業との間に一定の距離があるため、発信できるブランド表現や企業イメージに限界があります。一方、ユニフォームは従業員が顧客と実際に接触する場面で直接的に目に触れるため、その影響力が大きいのです。
ユニフォームは企業の「顔」として、サービス業などで顧客と接する際に、企業の文化や価値観を視覚的に、かつ感覚的に伝える重要な役割を果たします。洗練されたデザインや高品質な素材を採用することで、企業の信頼性やプロフェッショナリズムを表現でき、顧客に強い印象を与えます。実際に従業員がユニフォームを着用することで、企業の姿勢や特徴が顧客に伝わり、そこから企業に対するイメージが形成されていきます。こうした日常的な接点の積み重ねが、企業イメージの向上に寄与します。
ユニフォームリニューアルによる企業イメージの一新はオンワードコーポレートデザインにご相談ください
オンワードコーポレートデザインは、ユニフォーム導入を通したブランディング支援を行っています。
オフィス向けのユニフォーム、現場向けの作業服、接客業向けのサービスユニフォームなどあらゆる業種のオリジナルユニフォームを展開しています。
60年以上にわたる歴史があり、現在も約1,600社の企業のユニフォームに採用され、ブランディング支援実績も豊富です。
ブランドの方向性や価値の整理のためのワークショップも実施可能
ブランド価値やビジュアルアイデンティティの整理といった工程に社員様が参加いただきやすいように、ワークショップを実施することも可能です。ワークショップでは、ユニフォームの役割を説明する座学から、意見を引き出すためのグループディスカッションなどを実施します。
ユニフォーム提案だけでなく、社内外への発信もサポート
ユニフォームの導入にとどまらず、その後の社内外への効果的な発信も一貫してサポートしています。
コンセプトの策定やデザインの起案など、ユニフォーム導入のプロジェクトを密着取材した動画の作成や、メディアへのプレスの発信などにより、ユニフォーム刷新をより効果的にアピールするためのサポートも合わせて実施可能です 。
ブランディングに向けた施策を検討されている方は、ぜひご相談ください。
以下の資料では、オリジナルユニフォーム導入を成功させるためのオンワードコーポレートデザインのノウハウを紹介しています。
オリジナルユニフォーム導入を検討している企業様はぜひご覧ください。
DOCUMENTS お役立ち資料

業界や職種を問わず、ユニフォームはさまざまな企業で使用されています。
特に昨今は、大量生産されている既製品を活用するのではなく、企業がアイデンティティを表現する手段として、それぞれがオリジナルデザインのユニフォームを制作し、活用するケースが増えてきています。既製品では表現できない企業の姿勢を示す重要な要素です。
そこで本書では、オリジナルのユニフォームの導入ポイントや流れなど導入に向けて知っておくべき情報をご紹介します。
RECOMMENDED COLUMNS 関連コラム
-
 ブランドカラーとは?
ブランドカラーとは?
コーポレートカラーとの違いやカラーの使用時の注意点も解説ブランドカラーはブランドや製品・サービスの本質的な価値を表現する色であり、ターゲットやニーズに合わせて適切な色を選定することで、消費者への印象付けや認知拡大などに寄与します。ブランドカラーを使用する際には、色ごとの与える印象や特徴、ブランドが伝えたいストーリーを整理し、ロゴ・シンボルや制服など、カラーを使用する対象に応じて最適な戦略を描くことが重要です。
本記事では、ブランドカラーの概要や使用される所、使用する際のポイントなどを解説します。ブランドカラーの整備をお考えの方はぜひお読みください。 -
 アウターブランディングとは?
アウターブランディングとは?
インナーブランディングとの違いや成功ポイントについても紹介変化の激しい現代の市場において、企業は自社の価値や理念を明確化し、競合との差別化を図るためのブランディングを行う必要があります。その際には、社外向けの認知拡大を図るアウターブランディングと、社内でのブランド価値の共有・浸透を図るインナーブランディングをともに強化し、一貫したメッセージを発信することが重要です。本記事では、アウターブランディングとインナーブランディングの違いや、アウターブランディングを進める際のステップ、成功するためのポイントなどを解説します。アウターブランディングの強化や取り組みにご関心のある方はぜひお読みください。
-
 【目的別】周年行事・周年記念アイデア集
【目的別】周年行事・周年記念アイデア集
ブランディング効果を高めるポイントも解説会社の周年行事・周年記念のイベント開催は、顧客や取引先との関係構築やブランドイメージの向上、社員のモチベーションアップやコミュニケーションの活性化、エンゲージメントの醸成などさまざまなメリットをもたらします。イベントの効果を最大化するためには、社内向け・社外向けに目的を設定し、自社にとって必要な変化は何かを整理することが重要です。
本記事では、周年行事・周年記念のアイデアを社外向け・社内向けに分けてご紹介するとともに、イベントのブランディング・PRの効果を高めるためのポイントを解説します。